米糠(米ヌカ)を入手できなかったときの(孟宗竹 あく抜き 下調理の簡単レシピ)
 |
皮付きのままで、灰汁抜き(あくぬき)は簡単
たけのこは、毛のつやがよく根のボツボツが均等で立派なものを選びます。大きい竹の子は、量も多く歯ごたえもありますがアクもそれなりにあります。厚みがあるので火の通りも時間がかかりアクが抜きも大変です。場合によっては手持ちの大なべに入らない場合は、多少風味が落ちますが真っ二つや3つ以上にカットして入れるか皮を剥いてゆでなければなりません。小ぶりなものは柔らかく火の通りも食感もよく、竹の皮ごとゆでられるので竹の風味を逃さずにアクぬきできます。大きさに関しては、なにより家にある鍋の大きさと相談しましょう。
穂先があまり緑色でなく、黄色の強い物で小ぶりの物が、まだ地上に顔を出していない物で、身が柔らかく灰汁(アク)が少ないので料理しやすいです。酢味噌などで頂くと風味が豊かで酒の肴に合います。
ひらひらした皮は剥ぎ取って泥などが付いている場合は、たわしで軽く洗います。鍋が小さい場合は2分割、4分割すると早く煮えます。できるだけ鍋の大きさにあった小ぶりの筍を丸ごとゆでると、春の風味がたっぷり詰まった筍ができます。もし知り合いのところで掘る(頂く)ことができた場合、大きいものを少なくもらうより、小さいものをいっぱいもらったほうが便利です。
穂先があまり緑色でなく、黄色の強い物で小ぶりの物が、まだ地上に顔を出していない物で、身が柔らかく灰汁(アク)が少ないので料理しやすいです。酢味噌などで頂くと風味が豊かで酒の肴に合います。
ひらひらした皮は剥ぎ取って泥などが付いている場合は、たわしで軽く洗います。鍋が小さい場合は2分割、4分割すると早く煮えます。できるだけ鍋の大きさにあった小ぶりの筍を丸ごとゆでると、春の風味がたっぷり詰まった筍ができます。もし知り合いのところで掘る(頂く)ことができた場合、大きいものを少なくもらうより、小さいものをいっぱいもらったほうが便利です。
 |
 |
 |
| 竹皮にも風味が多くあるので、竹皮の風味を捨てずに竹の子に多くしみこませる為、皮は剥かずに、頭を斜めにカット | たけの子は中に小さな空洞があるので、立てに少し(1/3〜半分程度)切り込みを入れ火の通りを良くする。 | 包丁で多く切り込みはいれず、手で少し切り口を広げる、切り込みを手で広げると、切り口が閉じにくくなりゆで汁がしみこみやすい |
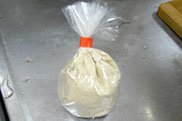 |
 |
 |
| 通常竹の子を売っているお店で小袋に小分けした米ぬか(黄色い粉状のもの)を無料でできるものですが米ぬかを入手している場合は通常の米糠(米ヌカ)でのアクぬき方法を参照ください。もらい忘れた場合、このページの米のとぎ汁かお米などで代用します。無洗米で無い通常の米を研ぐときにでるとぎ汁を捨てずに集めます。お米の場合は長めにゆでます。 | ||
 |
 |
 |
| 竹の子がしっかり漬かるようにとぎ汁か水を入れます。 | 1回目のとぎ汁で足りない場合は2回目と入れていきます。お勧めできませんが、それでも足りないようであれば、米または残りご飯を大さじ1杯程度足すなど。 | 日持ち(エグミをごまかす)をを良くする為、唐辛子を1〜3本入れる(一味等でも代用可、無くても可)、唐辛子に切れ目を入れると強めになるが、最終的に料理段階でほとんど辛さのは残らない |
 |
 |
 |
| 糠(ぬか)を一握り(適当)入れる | 煮る、沸騰したら直ぐ弱火に、アクが浮いてくるが、皮があるので際吸着しないので、お玉等でアク取りは不要 | 豪快に、吹きこぼれるので注意 汁を焦がすと後片付けが面倒に |
| 加熱時間は、風味優先20分ぐらい、 アク抜き優先は40分ぐらい |
 |
自然に冷えるまで待ちます。 |
| 20分(歯ごたえ有)〜40分(ふにゃふにゃ水煮風)程度弱火で | 竹串が根元部分にすっと入ればOK | そのまま冷ます、自然に放置して冷ます。水道水で冷やすと風味が損なわれます。 |
 |
 |
 |
| 触れる温度になったら、最初に中央に入れた切り目から剥きます。皮を剥くときにぬかがおおよそ取れるので、最低限必要なだけぬかを取る。多少残っても、ぬかは食べても害はありません、それよりぬかは栄養が豊富です。 | 穂先側を少し残して完成です。 | あとは使用する料理に合わせて! |
 |
下処理完了!! 食材として利用する。 更に水にさらすと”あく”が和らぎます!が筍のもち味である風味も。 |
 |
使い切れない場合は、水に浸して冷蔵庫に、水に濁りがある場合は濁りが消えるまで数回水を交換します。濁りがなくても水は毎日交換します。この方法で2,3日ぐらいはもちます。アクが強い場合もこの方法で和らぎます。 |
あくが気になる場合は、2時間水にさらす、アサリと炊き込む場合はあまり水につけずあくの感じが残るほうが・・・好みで。白い粉のようなカス状のものはアミノ酸の1つで、大量のチロシン(Tyrosine)が結晶化したもで栄養素の一つです。 | ゆで汁にはアク(シュウ酸やホモゲンチジン酸)が溶け出しています。 |
蓚酸(シュウ酸)は、とりすぎると尿道結石や腎臓結石の原因とされ、カルシウムを多く含む食材(アサリなどや魚料理など)と一緒に調理すると、カルシウムと結合して、えぐみを感じにくくなり、腸で吸収されにくいとされています。シュウ酸は水溶性なので、茹で時間を長くする、茹で上がったものを切って流水にさらすなどすれば更に少なくなりますが、風味もなくなります。 |
||
 |
もっと長持ちさせる方法は、1リットルに対し塩大さじ1杯入れ保存する方法と、更にそれに酢を100cc(カップ半分程度)があります。ただし使用するときに塩抜き(料理に使う前に1時間程度、水に漬けるて塩分を抜く)が必要です。ただし塩抜きしても多少塩分や酢(臭・香り)は残りますので料理時工夫が必要です。 |
| 米糠(ぬか)や米のとき汁でゆでると吹きこぼれやすいので、弱火にして注意してください。 米ぬかの臭いや、シュウ酸がだめな方は、重曹で茹でると、えぐみもぬかの匂いもつきませんが風味も市販の水煮パックに近くなります。重曹と糠をブレンドしたり量で調整する。胆石の原因とされるシュウ酸は、ワカメやクエン酸の多いお酢を料理に活用すると低減されるといわれている(根拠は不明)。 |
 |
 |
 |
| タケノコご飯 アサリか油揚げを入れるとさらに |
タケノコの煮付け 鶏肉も合います。 |
タケノコの味噌汁 ワカメもオプションで |

サイト
好奇心で
使ってみました
行ってみました
みやげ・その他